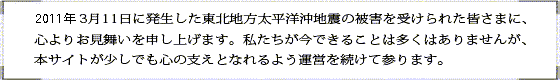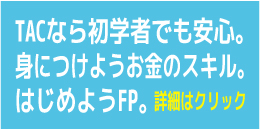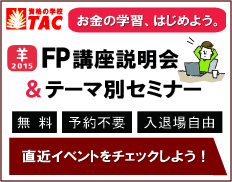■ 【賢者的考察】 昨今の子供のマネー教育とは
皆さん、こんにちは。 如何お過ごしでしょうか。 さて、今日は掲題のテーマ、昨今の子供は、お金について どのように向き合っているのかについて触れてみたいと思います。 みなさんは、小学生のころ、どのようなお金の教育を受けましたか? おそらくは、体系だった 「お金の教育」なるものを、小学生自分に受けた経験が ある方は、多くないのではないでしょうか。 かくいう私も、「おこづかい帳」なるものをなんとなしに記帳したり、お年玉を年間を通して 使ったりと、小学校時代に行っていたお金の扱い方は、その程度のものとしか、記憶にありません。 また、多くの家庭でも同じかと思いますが、高額なものは、例えばクリスマスの時になど、 別に買ってもらっていた記憶があります。 さて、幼少時におけるお金の向き合い方は家庭毎に様々だと思いますが、 例えば小学生に対する「お金の教育」は、現在はどのように行われているのでしょうか。 金融・経済大国でもある米国と、日本とを比較しながら、「子供のお金の向き合い方」について、 みてみましょう。 ■ 日・米それぞれの「おこづかい」はいくらぐらい? さて、まずは「おこづかい」の額について調べてみましょう。政府の調査機関である 金融広報中央委員会によると、調査結果は下記のようになります。(平成22年度の調査) ■小学校低学年 最も多く回答された金額 500円 平均額 949円 最も多い回答の金額帯 500?700円(21.7%) 次に多い回答の金額帯 100?200円(17.8%) ■小学校中学年 最も多く回答された金額 500円 平均額 896円 最も多い回答の金額帯 500?700円(27.3%) 次に多い回答の金額帯 1000?1500円(19.7%) ■小学校高学年 最も多く回答された金額 500円 平均額 1087円 最も多い回答の金額帯 500?700円(37.6%) 次に多い回答の金額帯 1000?1500円(29.9%) なお、調査対象は、何か欲しがった時に子供に買い与える形をとっている家庭で、その額は、 おこづかいには含まれていません。 ご覧のように、「小学生では平均月1,000円前後、中学生でも平均月2,500円ほど」という結果が 出ています。 一方、米国では、10歳以下の子どもが1ヵ月にもらうお小遣いの平均金額は、 なんと約1万1400円になるそうです。 ただし、この額は、洋服やおもちゃの購入費も含まれている額です。 そのため、上記の日本のおこづかいの額に、毎月や毎年、別途購入するモノの額を加算の上、 比較してみてください。いかがでしょうか。 なお、アメリカでは、お金を全て管理させ、その中で、忍耐や計画性を学ばせる習慣が 徹底しているといわれています。 ■ 学校による「マネー教育」の違い 日本では、定期的に小学校でお金について学ぶカリキュラムは組まれていません。 しかしながら、商店街と協力をした課外活動など、不定期にマネー教育を行っている地域もあります。 現在、英語学習の早期化などと同様に、マネー教育の重要性が理解されつつあります。 一方、米国では、子どもがお金について学ぶのは当たり前と考えられています。 幼稚園からハイスクールまで、発育段階に合わせたマネー教育の環境が、義務教育の時分から 整備されています。各幼稚園や学校では、経済教育NPO(非営利団体)などの協力を得た マネー教育プログラムを導入。生徒が実際に株取引を行ったり、 企業家や経済人が講師と なってビジネスシーンでの旬な話題やこぼれ話を披露するなど、大人も参加したくなる、 興味深い授業が展開されています。 そして、それらの教育の違いは、次のような調査結果に表れています。 日本とアメリカの大学生657人(日本312人、米国345人)を対象とした、金融教育に関する 調査によると、小・中・高等学校のいずれかで金融教育を受けた経験があると回答した人は、 日本が39.7%(124名)に対し、アメリカが72.2%(249 名)となり、約2倍の差があることが 明らかになりました(2012年3月/株式会社シタシオンジャパン調べ)。 今後は、文科省、日銀、日本FP協会などで様々な取り組みがされているため、上記の数値は 変化する見通しですが、現状はまだまだ、小学生のマネー教育の機会は少ないようです。 ■ 今後、小学生などの児童へ向け、どのようなお金の教育を行うべきでしょうか お金に対する向き合い方が、大きく異なる米国と日本。加速するグローバル社会の中にあっては、 英語学習もさることながら、ビジネス上での共通言語であるファイナンス知識も必須となるでしょう。 米国は、さまざまな通貨が流通していたり、クレジットカード社会であったり、日本に比べ医療費が かなり高額など、個人がしっかりとした金銭管理能力を持っていなければ、生活が難しい環境に あります。 日本においても、世界でも一番の超高齢化社会であり、医療費や年金などの社会保障費の増加、 消費税増税など、社会構造が大きく変化しています。同様にしっかりとした金銭管理能力が 問われています。 そのような日本社会において、幼少期から経済・金融の世界と 接点を持つことで、お金の大切さ、 お金を得ることの大変さを知り、社会生活の基礎知識や働くことへの意欲を養うことは重要です。 しかし、記帳や投資など、お金の一側面だけの学習にとどまらず、 「お金を稼ぐためにはどうすればいいのか」という仕組みから、考え、体験できる教育が、 ますます重要になることでしょう。 そして、それはまさしく、私たち労働者が日々行っているビジネスの世界でも共通のテーマで あります。 子どもは、子どもならではの、自由で柔軟な想像力・創造力を活かして、 楽しく「お金」について触れ、向き合える学びがあるとよいですね。 そして、その子たちが活躍する10年後、20年後には、より良い経済・社会を生み出すことを 願いたいものです。
日付0000-00-00 00:00:00