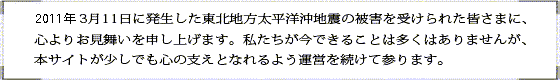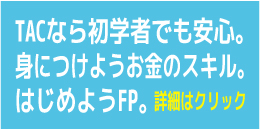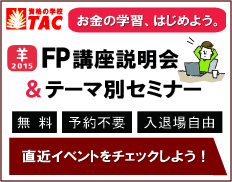■ 【賢者的考察】 「いずれ”サラリーマン職”は消滅するとしたら」
みなさん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。 揺れ動く社会情勢、見通しのきかない経済。 不安をあげればきりがありませんね。 そこで今回は、いっそのこと掲題のように、 「所属する会社だけに通用する”サラリーマン職”は 消滅するから、会社を選ばない、本質的な専門性を 身に付けよう」という主旨で、考察をしてみましょう。 そもそも、会社に所属して会社のために働き、 対価として給料を受け取る「サラリーマン」という働き方は、 どの国にも存在する“グローバルスタンダード”のように見えます。 しかし、その実、日本のサラリーマンはかなり特殊だといいます。 権威あるビジネス誌を刊行するプレジデント社のあるライターさんによると、 ”外国人に「あなたの仕事は?」と聞くと「会計をしている」と専門分野を述べ、 「どこでその仕事をしているのか?」と聞いて初めて会社名を答える。 自分のプロフェッション(専門分野)がまずあって、会社はプロフェッションを 活かす場所なのだ。”といいます。 そして、”日本のサラリーマンはプロフェッショナル(専門家)ではなく、それぞれの会社に 最適化されたジェネラリスト(総合職)で、その技能や経験は会社を離れるとなんの価値も なくなる。そんな働き方が成立していたのは、年功序列と終身雇用が前提にあったからだ。” としています。 しかし、その労働環境を支えていた日本の高度経済成長時代は既に終わり、 国際化や高齢化社会問題が山積し、今後も様々な局面に対応すべき時期にいます。 では、このような課題を打破することのできる「キーワード」はどういったものなのでしょうか。 それは、私たち、生活者・労働者個人の労働力向上ではないでしょうか。 このことは、国際競争が大前提になっている欧米諸国に目を向けると、より鮮明になります。 例えば、北欧諸国では、その能力向上に対する施策を、社会全体で構築・遂行しています。 スウェーデンでは、40歳になって 「自分のキャリアはもう先がない」と判断したら、 会社を辞めて大学に再入学し、 修士や博士を取得して専門性を高めて再就職するといいます。国からのバックアップもあるため、 大学の学費を無料にしたり、就学中は低利の融資で生活費が賄えるようになっているそうです。 その結果もあってか、労働者1人あたりの生産性は日本と比べて3割も高いといいます。 また、各種の意識調査で「世界一幸福な国」とされたデンマークも、ワークライフバランスで 世界の模範となっているオランダも、ほぼ同じ社会システムを採用しているといいます。 一方、現時点での日本には、本格的なキャリアの再設計制度はなく、40代以上なら、 スペシャリストとしてスキルを磨くよりも、なんとか定年まで逃げ切るための努力のほうが 合理的と考えるかもしれません。しかし、日本を代表する企業のリストラや、再就職の難しさが 聞こえて来る中、その逃げ切りが難しくなっている現状も浮き彫りになっています。 そこで、重要なことは、「自分の人的資本はどこにあるのか」を再確認し、企業に依存することのない、 人的資本=自身の価値を、今から高めることではないでしょうか。 そしてそのためには、「万が一リストラ対象になったとき、どうやってお金を稼ぐのか」といった意識を 常に持ち、長く培われたカチコチな固定概念を超えて、自己変革の一歩を進む姿勢が重要でしょう。 加えて、「時代が変わっています」「働き方が変わっています」ですので、 「自分が変わります」といったように、そんな簡単に自己変革をするのは難しいはずですから、 次の一歩を踏み出す勇気や、固定観念を覆すような想像力を強くすることが重要になりそうです。 決して、「私はもう年だし」「能力は低下し続ける一方だし」、 また「世間の流れについていけなくなっている」や「働くチャンスがない」など、そのような発想や 先入観をどんどん強くし、可能性を捨ててしまわないことを心がけたいものです。 そうやって、一歩一歩を踏み出すことで、自分では気づかない可能性や将来につながってゆくのでは ないでしょうか。 企業の看板が通用しない時代、あなたは何をやっている人と答えますか。 引き続き、考察を深めて参りましょう。
日付0000-00-00 00:00:00