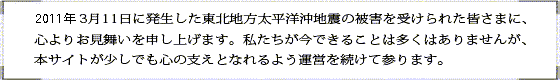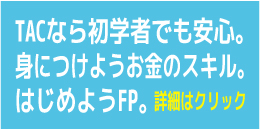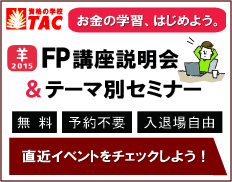■ 【賢者的考察】 「伝統技術を継承してゆくための経営体質とは」
みなさん、こんにちは。 めっきり寒くなってきましたね。 一日の寒暖の差も激しくなってきているようです。 どうぞご自愛くださいませ。 さて、みなさんは、「伝統工芸」と聞いて、どのようなことを イメージしますか? 私なぞは、例えば瀬戸の陶器や、こけしなど、 そのようなものをイメージします。 しかしながら、そもそも伝統工芸の定義は何だろうと思い、調べたところ、 下記の定義がありました。 1: 日常生活で使われている工芸品である 2: 手工業である 3: 技術、原材料が100年以上受け継がれている 4: 一定の地域で産業として成り立っている そのような伝統工芸品でありますが、その工芸品を生産する人や 組織の経営事情というのは、なかなか知る機会もありませんね。 そこで今日は、日本の伝統的技術を商材とする企業を、 外国人ビジネスマンの視点で捉えた事例をご紹介したいと思います。 ここ日本に、小西美術工芸という会社があります。 1636年創業で、日光東照宮を作った際に全国から集まった職人の中から、日光に残った職人が 設立した会社。現在では全国の建造物漆塗のシェア40%を占める文化財修復業の最大手企業。 そしてまさに、おそらくは関連他社も同様に、この企業には、経営上の様々な問題があるといいます。 そう指摘するのは、元ゴールドマンサックス証券のイギリス人アナリスト、 デービット・アトキンソンさん。 偶然の出会いを経て、 同社の代表取締役社長へと異色の転身とあいなり、 問題解決に取り組んでいます。 では経営上の様々な問題とはどのようなものでしょうか。 そう聞くと、私たちは、「人手不足による後継問題」や、「文化財保護予算の割り当て問題」と 考えたりすることでしょう。 しかしながら、アトキンソンさんは、そういった問題を派生させる、「経営体質」が問題とし、 次のように述べています。 「職人の世界は聖地だと思っていました。しかし、自分が経営者として参画した時には、 小西美術工芸は業界最大手にも関わらず、経営から品質までさまざまな問題がありました。 だから、自分が必要とされたのだと思います。そして、自分が改革しようとした時には、 特に年配の職人からものすごい反発がありま した。国の予算がないから、業界が疲弊している。 いい仕事をしても、でたらめな仕事をしても同じ給料をもらえるし、誰も見ていない。 いい仕事をしても無駄だ、だから手抜きでいいという風潮もあったのです」 つまり、伝統工芸産業は、国や地域によって保護され、向き合うお客さんが限定され、 然るべき評価をがされない現状があるとしています。 だからこそ、マーケットまたは企業が、職人に対して何らかの評価軸を持たせなければ、 現場から努力が生まれない可能性があるとしています。 そこで、アトキンソンさんが経営者として小西美術工芸に来た際に、最初に改革したのは、 現場の責任者を年配の職人から若い職人へと変えたといいます。 「年配の職人には親方を外れてもらい、工房に行ってもらいました。漆塗の現場は外仕事なので 体力が重要ということもあります。やはり年配の職人は力 が衰えている。 人によっては情熱も冷めていますので、仕事の質が下がる傾向もあります。 だから、40代の職人に現場の責任者になってもらいました。 すると、同じ人が作ったものかと驚くくらい、品質が変わったのです」 また同時に、全体の4割を占めていた非正規雇用の職人を、全員正社員に変え、 若い人に責任を持ってもらい、同時に昇給をしたといいます。 すると、手抜きが減って品質が上がっただけでなく、利益も増えたのです。 きちんと現場での経営改革を進め、現場が出している付加価値に合わせて評価を行うだけで、 設備投資や研修、若い人を雇うのに必要な、まっとうな利益を出るようになったといいます。 さらに、アトキンソンさんは、「伝統工芸」の将来は、世間で言われる風説と実態は違うと、 指摘をしています。 「伝統工芸に興味を持つ若い後継者がいない、というのは幻想です。 それは自分の立場を強くしようとしている年配の人が言っている言葉だと思います。 やりたい若い人はいるのですが、予算が増えない中、寿命も延びて、現役が強いので、 なかなか席が空かない。」 「それと、業界として然るべき採用活動をしていない。この業界で幅広く、工夫して、 採用求人を出しているのは私たちの会社だけだと思います。 求人を出すと若い人の応募はかなりありますよ。それが事実なのです。 後継者がいないのは本人たちの問題も大きいのではないでしょうか。」 これが、異業種からきた外国人が、日本の伝統工芸会社の社長として捉えた実態と課題、 そして変革の途です。 この一連の取り組みは、「成長・発展する経営体質とは何か」について、気付きを与えてくれる、 一つの好事例のように思います。 たとえ従来のやり方で、300年存続してきたとしても、今後も存続してゆけるとは限りません。 こと、外的要因にさらされない産業は、時流を捉えていないケースがままあることを示しています。 伝統技術は守られ受け継がれるべきものだが、その技術を受け継いでゆく組織自体は旧態依然であるべき ではなく、時流に沿って適合してゆかなくてはならないのでしょう。 そうすることで、長年に渡って守られ受け継がれてきた伝統技術が、当該組織の存在意義でもある、 さらに後世へ受け継ぐことにもつながるのでしょう。 皆様はどのようにお考えでしょうか。 ぜひ考察してみてください。
日付0000-00-00 00:00:00