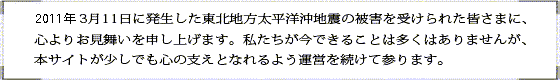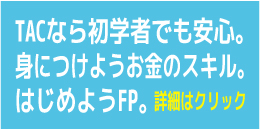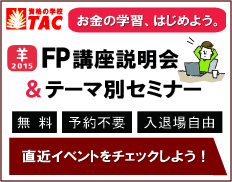■ 【賢者的考察】 「なぜ働きますか?」
みなさんこんにちは。 寒さととともに、年の瀬も迫ってきました。 まだ数週間のありますので、一年の振り返りには 未だ早いかもしれませんが、現役で働かれている方、 これから社会に飛び込んでゆく方には是非、 今一度考察していただきたいテーマがあります。 それが今回の掲題にございます「なぜ働きますか?」です。 社会は、既に目に見える形で変化を続けています。 雇用事情も明らかに10年前と違っていることでしょう。 そして今後も更に変化することが予測されています。 そしてこの変化は、ある種当たり前のことのはずですが、長年の日本文化、雇用環境に なれてしまうと、いえ、なんであれ、習慣化されたものを変えてゆくためには、様々な労力や 発想、視点の変更を余儀なくされることでしょう。 そこで、今回の「働く」ことの本質的な意味合いを深めるべく、掲示しているわけであります。 前置きが長くなりましたが、早速考察をしてまいりましょう。 まず、この問いに対して自分なりの答えを、早期に持つ必要があると感じます。 就活だけの話だけではなく、それ以上に、将来のビジネスライフから翻って考えても、 「なぜ働くのか」ということに対して、自分なりの意味を持った論理的帰結をしておく必要が あると思うのです。 ヤン・カールソンという著名な経営者は、著書「真実の瞬間」の締めでこのような寓話を使っています。 ある日、一人の旅行者がバルセロナのサグラダ・ファミリアを訪れました。辺りを歩いていると、 道端で一人の石工が石を削っています。好奇心旺盛な旅行者は、その石工に声をかけました。 「あなたは、いったい何をしているんですか?」 するとその石工は、迷惑そうな顔をしながら腹立たしげにこう言いました。 「見て分からないのか。このいまいましい石を削っているんだ!邪魔だから、向こうに行ってくれ。」 旅行者は慌ててその場を離れ、しばらく歩いていると、別の石工が同じように石を削っています。 その旅行者は、懲りずに先ほどと同じ質問をしてみた。 するとその石工は、晴れやかな顔をして誇らしげにこう答えました。 「よくぞ聞いてくれました。私は今、世界で一番美しい大聖堂の基礎を作っているんですよ!」 この文章を分解してみましょう。以下の3つに分けられることでしょう。 1.自らの選択によりどう働くかを選択できるということ 2.その選択に対して自らの解釈及び意味付けを行うことができるということ 3.自らの解釈及び意味付けにより、充足も絶望もできるということ まず、人は良い仕事をすることもできるし、適当に仕事をすることもできます。大聖堂の基礎を 適当に作る人もいるでしょうし、エクセレントな仕事をする人もいます。これはその人の選択次第です。 そもそも働くのか働かないのかも自らの選択によって決めることができます。 次に、その仕事をする上で、仕事にたいしての自らの解釈や意味付けをすることができます。 (1と2は逆になる場合もあるかもしれません)。 例えば、「自分の人生は全く意味がない。よってこの暇な時間をなんとか埋めないといけない。 だから、石を削るために手を動かしているんだ」という人もいるかもしれませんし、 「自分の人生は意味のあるものである。この大聖堂が出来上がれば、多くの人達の感動や幸せを 見ることができる。その大聖堂は基礎がなければ、成り立たない。 今、私はその大聖堂の基礎を作っている」という人もいるかもしれません。 自らの解釈と意味付けによって、「何のためにやっているんだ」と虚無感に苛まれることもできますし、 「偉大な仕事をした」と充足することも可能であるという事です。 さらに、仮説ではありますが、完成した暁の全容を思い描くことが出来てしかもその建設工事の一翼を 担っている石工は、ただ目前の岩を見つめてうんざりしている石工より、はるかに生産的だと思います。 要するに成果にも直結することであると思います。 充実したビジネスライフを送る上で働くことを選択したのであれば、解釈や意味付けに対し、論理的な 帰結をしておくことは非常に重要でしょう。 それでは、上記を踏まえた上で、「働くこと」や「仕事」についてどのような事が考えられるでしょうか。 ◎「仕事の報酬とは何でしょうか?」 例えば「仕事の報酬は、給料や収入だ。」と答える方もいると思います。 確かにその通りですし、そうだと思います。 しかし、本当にそれだけなのでしょうか? その道のエキスパートにおいて、例えばスティーブ・ジョブスの書籍に、 給料のために仕事をするといった表現はなかったですし、 ドラッカー、アインシュタイン、リンカーン、ダーウィン、エジソン、メイシーもしかりでしょう。 「別にこのような偉人になるつもりはない」と思われるかもしれません。 しかし、その道を極めた人物として働き方でも学ぶ部分はあるはずです。 では、仕事の報酬が給料や収入以外にあるとすると、それは何なのかということです。 ここからは他者からの言葉も引用しながら進めていきたいと思います。 仕事の報酬とは、目に見えない報酬であり、以下の三つに集約されます。 1:「能力」 2:「仕事」 3:「成長」 ・「能力」とは、当然仕事をする上でよい仕事を残そうということで、能力が磨かれるでしょう。 ・「仕事」とは、能力を磨くことで、世の中に対して優れた「仕事」を残すことができるでしょう。 ・「成長」とは、仕事での困難を仲間と一緒に解決することで、人間として「成長」ができるでしょう。 こういった見えない報酬まで考えて仕事ができたのであれば、 仕事を楽しむ方法が今以上に広がることでしょう。 ◎得ることだけが仕事なのか? とはいえ、お伝えした「能力」「仕事」「成長」を得ることが仕事の報酬なのかというと、 それだけでもないという意見があるやもしれません。 その答えが、次の一文に集約されているやもしれません。 『掃除道』鍵山 秀三郎 ・ 一つ目の幸せは、してもらう幸せです。 ・二つ目の幸せは、自分でできるようになった幸せです。 ・三つ目の幸せは、人にしてあげる幸せです。 人がしてほしいことをすると、喜ばれます。そんな人は頼りにされます。人にモノを差し上げる、 自分の身体と時間を使って何かをして差し上げる、相手の喜びをわが喜びとする。 この幸せを大事にしていただきたいのです。 「してあげる幸せ」は三つの幸せの中でも最高の幸せです。 "自分でできるようになる"といった「能力」「仕事」「成長」を報酬として得ることも、 充実した人生かもしれません。しかし、それ以上に「能力」「仕事」「成長」を誰かに差し上げる。 こういった世界があるということではないでしょうか。 「なぜ仕事をするのか」に関して、明確な人と不明確な人ではパフォーマンスに大きな差が 生まれるでしょう。もし、今自分が持っている能力を遺憾なく発揮しながら仕事がしたいならば、 「なぜ仕事をするのか」についてしっかり考える必要があります。 そして、就活する上でも「なぜ働くのか?」について考えるべき理由があります。 なぜならば誠意を役立てることを前提に、誠意を役立てられる、誠意を役立てたいと思える 会社を選ぶ視点も必要だからです。 「給料」「収入」は使い果たせばなくなってしまいます。 「能力」は技術革新や環境の変化によって価値が失われるかもしれません。 「仕事」はいつの日か物理的なことから存続が難しくなる。 または、人々の心から失われてしまう可能性があります。 「成長」は生涯を全うした時に、失ってしまうのかもしれません。 しかし、「誠意を役立てるという人間性」というのは、人が存続し続ける限り、人から人へと 存続するのではないでしょうか。 そうあって欲しいものですね。 皆さんも是非、この年末年始、「なぜ働くか」について、考察を深めてみてはいかがでしょうか。 クオリティの高い仕事の実現に向け、ご自身で、ご自身の信念を、新年に纏めてみる・・・ おっと、失礼いたしました。以上でございます。
日付0000-00-00 00:00:00