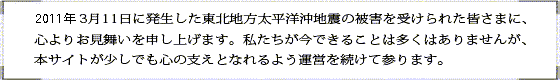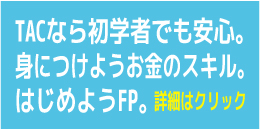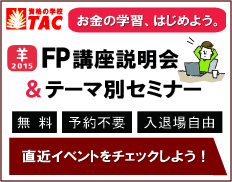■ 【賢者的考察】 「個人を磨く」
新年度が始まった。昨今の経済政策により、今後の日本社会、経済に対し期待を抱きながら 新年度を迎えた人も少なくないだろう。 しかし、その期待通りの世の中となるかどうかは、この時点で誰にもわからない。 だがその不確実性の中で、確実性を高めることはできる。 勿論、経済は様々な影響を受けながら成長、衰退するものであるから、一国民の行動が、 経済に直接関与するものではないだろう。 しかしながら、経済も人の手によって創造、輩出されている。 多くの個人、すなわち多くの国民が行動すれば、経済の成長に寄与することがあるだろう。 ではどのような行動が、経済に寄与してゆくのか。 下記の、4月1日付けの日経新聞社説から抜粋した文言では、この行動を「個人をもっと磨くとき」としている。 -------------------------------------------------------------------------------------- 資源の乏しい日本の最後のよりどころは人材である。 個人が自らの力を底上げしない限り、企業も国も競争力が高まらない。 変化の速いグローバル経済のなかでは、問題をすばやく分析し、 解決策を導き出す能力がますます求められる。 中小企業に至るまで海外勢との競争を強いられる現実を考えれば、英語などの語学力は欠かせない。 財務や会計、法務といった専門分野の知識もできるだけ深めておきたい。 そのためには、年齢にかかわらず自分を磨きつづけることが大切だ。 経済協力開発機構(OECD)の加盟国は、平均して大学生の2割超を25歳以上が占める。 社会に出た後に学び直すことが少ない日本では、この比率が2%程度と極端に低い。 社会人になって初めて学びの大切さが分かったという経験は、多くの人に共通する。 企業が従業員の研さんのために有給休暇などを使いやすくするといった手立てをとることも、 経済再生の担い手を増やすための一歩となる。 -------------------------------------------------------------------------------------- 老若男女問わず、「個人をもっと磨くこと」は、その個人に対し様々な機会をもたらす。 例えば、自身の資産化による、企業や社会に対するより多くの貢献、啓発による充実感などである。 また共学者との交流などに刺激を受ける方もあるかもしれない。 また、「個人を磨くこと」は、別段、高いスキルの修得や専門的知識の修得、座学などを指していない。 学ぶべき対象、学び方は各人の思考、興味、関心により選択するのが良いはずだ。 そもそも、経済は様々な社会問題を抱えながら成長をしてゆくことを考えると、 むしろ特化した知見のみで牽引される成長は、健全ではないからである。 海外では、学費無料のオンライン“大学“が活況で、ある種、教育改革ともいえる口火が切られている。 その受講生が持つ、学習する意志は、今後の社会において、必要不可欠なものといえるだろう。 今年度、学習する機会をもっていない方は、心機一転、この機会を積極的に持つことは、 日本社会はもとより、各個人にとって価値のあることになるだろう。
日付0000-00-00 00:00:00