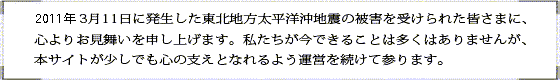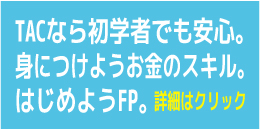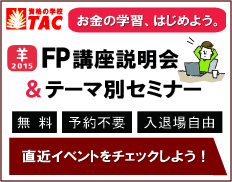■ 【賢者的考察】 「グローバル社会の中で ” 働く ” を考える」
皆さんこんにちわ。 今や社内公用語を英語とするなど、国際社会に 対応するべく、多くの日本企業が躍起になる昨今。 今日ほど国際社会に対する意識の高まった時代も ないのではないでしょうか。 そこで「賢者的考察」のコーナーでは、不定期ながら、グローバル社会の中で日本はどうなるのか、 どうあるべきか、考察をしてゆきたいと思います。 さて、みなさんは、「協同組合」ってご存知ですか? 協同組合というと最初に思い出すのが、生活協同組合ではないでしょうか。 そしてその協同組合という組織形態に、 不況が長引き企業の雇用が回復しない日本の明日を切り開く力があるとも言われています。 先日、NHKさんの「クローズアップ現代」で「協同組合」について特集されていました。 番組中に紹介されていた組織では、皆さんが「経営者」でした。 この職場では、自分たちが出資して、自分たちで仕事をみつけて経営していく「協同労働」という 仕組みで動いているのです。 また、番組中に登場する豆腐店では、一人5万円を出資すれば、 誰でも経営者になることができ、 製造だけなく商品開発や経営方針、そして月々の給料も自分たちで決めるのだといいます。 こうした「協同労働」の職場では、「すべての議論で決める」「地域の課題解決で仕事おこし」などの 特筆すべきポイントがあり、この豆腐店では、地域に密着して、ひとり暮らしの高齢者向けに、 お弁当の宅配サービスも始めているといいます。 こうして地域に密着した仕事を新たにおこしをすることで、150人もの雇用を生み出しています。 このような協同労働は、すでに日本全国に広がり、その数は、1000を超えるといいます。 また、世界に目を転じると、世界でもっとも注目されるスペインの協同組合、 「モンドラゴン協同組合」は、スーパーマーケットの経営だとでなく、家電の製造・販売など、 280を超える事業を手がけ、組合員は、8万3000人にものぼるといいます。 いわゆる一般企業では、働きがいを感じられない人も、こうした協同労働の場では、 イキイキと働いているといいます。 グローバル経済の発展とともに、格差が拡大していく中、どうやってこの問題を解決できるのか。 「協同労働」に解決のヒントがあるのかもしれません。
日付0000-00-00 00:00:00